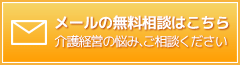介護・福祉事業の人事制度(キャリアパス)・設計・運用
御社はこのような人事制度になっていませんか?
- 人事制度が単に賃金を決めるものになってしまっている
- 人件費削減が経営者の本音である
- 職員も評価されることへの反発がある
昨今の介護ニーズの多様化・高度化に対応し、質の高い技術やサービスまた、同業他社との競争力を持って経営を行っていくためには、介護職員の安定的な確保とその資質向上が不可欠です。介護職員のキャリアパスを検討していく上では、入社時点、一定の実務経験を経た後など、それぞれの段階ごとに求められる役割や能力を明確にし、その能力の修得を目指した資格・研修体系を会社がバックアップし、構築していく必要があります。
そのためには、介護職員の仕事に対する満足度を向上させ、やりがいに満ちた介護職員を定着・成長させることを通じて、良質な介護サービスの提供によるご利用者の満足度を高めることに取り組み、「経営の安定化を生む好循環」を生み出す確立できるようなキャリアパスを整備していくことが大切です。
介護職員一人ひとりが、目標を持ち、目標を達成する為に最大の努力が出来る環境を整えたなら、経営者の皆様の苦悩は大きく軽減されるのではないでしょうか?
当事務所では、介護職員のやる気を引き出し、健全な組織風土を確立させるという善循環システムの構築を最大の目的として、人事制度の見直し・導入をサポートします。
以下に一つでもチェック項目があれば人事制度をお作りいただくことをおすすめします
- 人事制度(評価制度や賃金制度)がない
- しっかり基準を持った評価制度も賃金制度を作りたい
- 評価も賃金も経営者の経験にたよっている(いつも不満を言っている職員がいる)
- 貢献度に応じた賃金制度を導入したい
- 部下を指導して育てることができない管理者がいる(目的意識もなく仕事をやっている介護職員が目立つ)
- 評価者によって部下の評価にばらつきがある
- 事業継承を考えているが、後継者のリーダーシップが心配である
人事制度の本来の役割とは?
人事制度の本来の役割は、「介護職員の成長を支援すること」です。 介護・福祉事業所にとって「職員が成長する」ということは、結果として「事業所の業績向上」に繋がります。
最も多い「退職理由」とは何でしょうか?実は、職場の人間関係でも賃金額に対する不満ではないのです。「この会社にいても “やりがい” がない」「会社の“将来ビジョン”が分からない」・・・だから、退職するのです。
経営者は、職員に対して、「この会社にいると自分が成長できる」「信頼できる仲間と仕事ができて楽しい」という実感をもたせることができるかどうかが、会社の成長における最大の鍵となります。
人事評価制度や賃金制度は多くの会社が導入しています。
しかし、評価と処遇(賃金・賞与、昇給・昇格・昇進、退職金)がしっかり連動をしているか?その仕組みが経営理念、就業規則や諸規程と同じベクトル(方向性)であるか?の視点からみるとほとんどの会社では不鮮明というのが現状です。
不鮮明であるかぎり、会社(経営者)と介護職員の信頼関係を築くことは難しくなります。
やるべきことは、事業所(経営者)と介護職員、上司と部下の評価や考え方のギャップを埋めることです。ギャップがあるかぎり、部下の指導はできないはずです。本来の人事制度は、このギャップを埋める役割をはたします。当事務所では、経営理念(経営者の想い)を基にして、以下のような仕組み構築のご支援を致します。
- 組織体制に連動した等級フレームを定める 資格等級制度
- 明確かつ公平な考課(評価)基準を定める 考課(評価)制度
- 評価にしたがって賃金(昇給・賞与)を定める 賃金制度
- 評価にしたがってステップアップ(昇給・昇格・昇進)を定める ステップアップ制度
- 評価結果のフィードバックにより介護職員の成長をしっかりサポート(教育)する 教育研修制度
人事制度は介護職員一人ひとりが理解し、活用できなければ無いのと同じです。
人事制度運用のポイントは、評価対象者の職員の皆さま誰もが理解ができる「分かりやすい」ものであることです。それではじめて介護職員一人ひとりが、「会社にしっかり評価してもらえる喜び」「自分の処遇を上げるためには会社の発展が不可欠であること」を感じてくれるようになるのです。
介護・福祉事業所は、今まで以上に職員満足度を高め、職員はご利用者の満足度を高めていく。両方がかみ合うことで、さらに会社の業績アップに繋がります。
この一連の流れを可視化し、組織的に「仕組み」にしたものが『人事制度』です。
私共がご提案する人事制度の特徴
「賃金を決めるための人事制度」から「職員の成長・働きがい・満足度向上のための制度」へ
人事制度の浸透は、組織全体で取り組んでいかなければいけません。 押しつけではなく、職員一人ひとりが明確な目的をもち事業所に貢献する、そして貢献したことを実感できる制度にしなくてはいけません。
特徴1 評価基準が明快なため、職員のやるべきことが明確になります
「会社が職員に期待することは何か?」(何をどのように評価するのか=職員は何をすべきか)を予め明快にします。職種(ヘルパー、介護支援専門員、看護師、等)や階層(管理職、一般職、等)ごとに「人事評価シート」を作成します。このシートにより、職員本人の自己成長はもちろんのこと、管理者による部下の指導内容も明確になります。
特徴2 評価結果が、賃金(昇給、賞与配分)に連動します
多くの事業所の評価制度では、人事評価の結果がどのように処遇に反映されているのか職員は知らされていません。これからは、処遇決定の仕組みを明快にして、事前確認できることで、職員が自らの目標を定めることができ、モチベーションアップに繋がります。
特徴3 事業所の業績も賃金(昇給、賞与配分)に反映します
昨今の厳しい経営環境においては、外的要因により会社の業績が伸び悩むこともあるでしょう。
このようなことを想定して、事業所の業績も職員の賃金とリンクさせます。
「会社の業績が○○の場合はどれくらい昇給があるのか」を事前に明らかにしておくことがポイントです。
このことから、職員本人の評価だけではなく、事業所の業績もアップさせることの大切さを理解すると同時に職員の一体感が生まれます。
特徴4 組織的に適正に評価をすることで、不平・不満を失くします
多くの介護・福祉事業所では、評価は直属の上司または経営者自らが行っていますが、これからは、管理者が集まって職員全員の評価を行います。当然初めのうちは各管理者によって評価にバラツキはでます。しかし。回数を重ねるごとで組織的な評価が固まってきます。
これにより、各々職員の評価は会社が統一基準に基づき決定することになります。
したがって、一般的な「人事考課者訓練」は行う必要はありません。
特徴5 フィードバック面接で上司が部下に評価結果と次の成長のためのアドバイスをします
職員が高い目標を目指したとしても、目標達成度や成長度は各々職員によって差があります。
大切なことはその差ではなく、各々の職員が自ら評価結果を確認することで次の成長を目指すように促してあげることです。管理者が部下を直接指導することで、部下との信頼関係を築き、会社の組織力の底上げにもつながります。
介護・福祉事業所の人事制度 の見直し・作成の流れ
当事務所では、次のような順番で人事制度を見直し・作成させていただいております。
| ステップ1 人事制度基本方針の確認 |
|---|
|
| ステップ2 資格等級制度作り |
|
| ステップ3 評価制度作り |
|
| ステップ 4 賃金制度作り |
|
| ステップ 5 ステップアップ制度作り |
|
| ステップ 6 社内説明会資料の作成と社内説明会の実施 |
| 人事制度は職員が活用できてはじめて効果(介護職員の成長⇒事業所の業績向上)を発揮します。 運用前に職員に説明を行い、不安な部分や疑問点をしっかりと解決しコンセンサスをとります。 |
| ステップ 7 就業規則(賃金規程)の変更・届出 |
| 各種手当の統廃合や金額の見直し等による、就業規則(賃金規程)の変更・届出を行います。 |
| ステップ 8 評価決定と教育研修制度(フィードバック)の実施 |
したがって、適切なフォロー(特に初年度は旧賃金額を保障する、上司によるマンツーマン教育等) を行います。 |